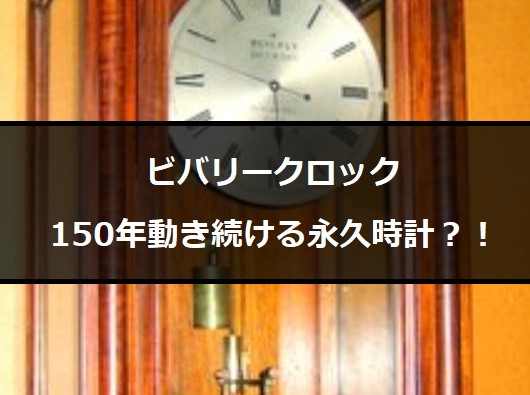永久機関Fileの時間がやってまいりました!
今回の「永久機関File」は、時計界のミステリー&レジェンド級の存在をご紹介します。
その名も…
ビバリークロック(Beverly Clock)!
なんとこの時計、1864年に動き始めてから一度もゼンマイを巻かれていないのに、今もなお動いているという超ロマンあふれる逸品。
そんなこと…ありえるの!?と思ったあなた、今回も科学とちょっぴり夢を交えて、ビバリークロックの秘密を紐解いていきましょう!
🕰️ビバリークロックって何者?
- 製造年:1864年(明治維新より前!)
- 設計者:アーサー・ビバリー(Arthur Beverly)
- 場所:ニュージーランド・オタゴ大学
- 特徴:一度も巻き上げていないのに動き続けている
動いている様子は以下の動画などで確認できます。
これだけ聞くと、「いやいや、それもう永久機関じゃん!?ズルい!」って思いますよね。でも安心してください。ズルじゃありません。
この時計は、ちゃんとした自然のエネルギー源を使って動いているんです。
🤔永久機関?いえ、”ほぼ”永久クロックです
ビバリークロックは、いわゆる「永久時計」の一種として19世紀に制作されました。

そもそも「永久機関」とは、「外部からエネルギーを一切受けずに、無限に動き続ける装置」のこと。
でもビバリークロックは、ちょっとだけ違います。
実際には「自然からのエネルギーを少しだけもらって、ほぼノーメンテで150年以上動き続けている」んです。
そのエネルギーとは……
🌡️原理は気温変化&空気のふくらみ!
ビバリークロックのしくみは、ちょっとした理科の実験レベルで説明できちゃいます。
🔧どうやって動いているの?
この時計には、約28リットルの密閉された空気の入った箱が組み込まれています(1立方フィート)。
毎日の気温の変化によって、箱の中の空気はわずかに膨張・収縮を繰り返します。
この変化によって、ダイヤフラム(膜のような部品)が押されて、おもりを持ち上げるための小さなエネルギーが生まれるんです!
具体的には…
🌡️ 気温が1日で6°F(3.3°C)変化するだけで、
⚖️ 1ポンド(約450g)のおもりを1インチ(約2.5cm)持ち上げられる圧力が発生!
💡 これは13mJ(ミリジュール)、もしくは約3.6μWh(マイクロワット時)程度のエネルギー。
なんと、これだけで時計を1日動かすには十分なんです!
エネルギーの供給源は【気温】と【大気圧】の変化。つまり…
自然界に毎日無料で提供されている、微々たるけど確実な力!
🔁「ダイヤフラム → 巻き上げ機構」への力の伝達プロセス
ダイヤフラムでの巻き上げは、以下のような仕組みです。
💡まず前提:どんな力が発生しているの?
- 密閉された空気室が気温変化や気圧変化で膨張・収縮する
- その体積変化に応じて、ダイヤフラム(薄い金属の膜やゴム製)が押されたり引かれたりする
- ダイヤフラムは「空気の圧力変化」を物理的な運動(押し出し or 引き込み)に変換する
ここまでは簡単ですよね。
🧭次に:その運動を「ゼンマイ巻き上げ」に変換する方法
ここからが工夫の見せ所!
✅ 1. ダイヤフラム → レバー機構へ
- ダイヤフラムの動きは「非常に小さな力とストローク(動く距離)」です
- それをレバー(てこ)やリンク機構を介して拡大 or 集中させます
- 例えば、ダイヤフラムに接するロッドが上下すると、その動きをレバーでトルクのある回転運動に変えられます
✅ 2. レバー運動 → ラチェット or 歯車へ
- レバー運動をそのまま巻き上げ用の歯車(ラチェット機構)に接続
- 歯車は一方向にしか回らない構造にすることで、徐々にゼンマイやおもりを巻き上げる
✅ 3. 巻き上げたおもりで、普通の重力駆動時計のように動作
- 最終的には、持ち上げられたおもりの重力で時計が駆動されます
- 時計の本体は、昔ながらの「おもりが下がって時間を刻む」方式です
🛠️実は一度も止まったことがない…わけじゃない!
「150年間一度も巻き上げてない」=「止まってない」
…ではありません!
⚠️実はこんな時に止まってます👇
- ⏹️ 機械内部の清掃やメンテナンス
- 🛠️ 機構の故障や微調整
- 🏫 大学内の物理学部が引っ越ししたとき
- ❄️ 室温が一定すぎて、気温変化が少なくなったとき
つまり、ゼンマイの巻き直しはしていないけど、物理的に停止した瞬間は何度かあるということ。
そして面白いのは、
🌡️ 環境がもとに戻ると、時計は自動的にまた動き始める!
これぞ“半分天然、半分人工の自己再起動装置”って感じでロマンですよね。
🧪永久機関の敵、それは「劣化」!
理論上、「気温さえ変われば永久に動く」とされるビバリークロック。
ですが、どんなメカでも避けられない敵がいます。
それは…
物理的な摩耗、潤滑油の劣化、パーツの経年劣化!
とくに歯車や軸などの部品は、150年も動いていればいくらかの摩耗が起きますし、潤滑油も揮発や酸化を免れません。
つまり、ビバリークロックが止まるとしたら、「原理」ではなく「素材」が限界を迎えたときなのです。
なんだか哲学的ですね。
時間を刻む装置が、時間に負けて止まる日が来るかもしれないなんて…。
🧭なぜこの時計が面白いのか?
- ✨ 実在する「ほぼ永久機関」
- 🌱 自然エネルギー活用の先駆け的アイデア
- 🧠 科学・工学・哲学が交差する魅力
- 🕵️ 「動いてるけど永久機関じゃない」矛盾のような存在
✅まとめ:ビバリークロックの魅力を総ざらい!
- 1864年にアーサー・ビバリーによって作られた時計
- 一度もゼンマイを巻き直さず、150年以上ほぼ継続して動き続けている
- 原理は気温変化や大気圧変動による空気の膨張と収縮
- 完全な永久機関ではないが、「ほぼ永久クロック」と言える存在
- いくつかの理由(メンテ・移動・気温安定など)で停止したことはある
- 最終的に止めるのは「原理」ではなく「物質的な寿命」かも?
🚀おまけ:もし自宅にあったら?
…気温が変わる部屋じゃないと動かないので、
エアコンガンガンの無窓部屋には不向きです!(笑)
でも、これを応用すれば、
- 自然の気温変化で充電する小型ガジェット
- 自律動作する温度モニタリング装置
…なんて未来の技術にもつながるかも!
以上、永久機関File22:ビバリークロックでした!
次回のFile23も、摩訶不思議な“永遠を目指す”機械たちをご紹介予定です!