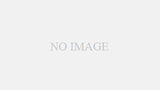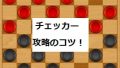岩手県の花巻には、金婚漬(金婚漬け)という伝統的な漬物が存在します。これはなぜ金婚漬けと呼ばれているのでしょうか?その由来や作り方などを解説していきます。
金婚漬けとは?何の具材の漬物?
金婚漬けとは、岩手県の花巻を中心に作られている、伝統的なお漬物です。

見た目としては、うすい茶色っぽいウリが外見になっていて、その断面には、ほかの具材が詰まっているのが確認できます。
見た目的にもカラフルで、断面に詰まっているのは金太郎あめのような食品を連想させます。
この美しい断面によって金婚漬けは「漬物の工芸品」とも呼ばれ、金婚漬けの大きな特徴といわれています。
味としては、作る過程でしょうゆ漬けをしたものなのでしょっぱめの漬物という感じらしいです。
金婚漬けの具材
金婚漬けの気になる具材は何なのでしょうか。
外側は先ほども書いたようにウリになっています。また、ダイコンやキュウリなどでも作られるようです。
内部の具材は、ニンジン、コンブ巻き、シソの葉、ゴボウなどが入っています。
作り方としては、
- ウリのわたを抜いて洗って塩で下付けをする。
- 醤油につけたニンジンやゴボウを切ってシソとコンブでまく。
- 巻いたものをウリの中に詰める。
- みそに一か月以上漬ける。
というのが基本的な作り方となっています。
漬ける期間は半年から一年にわたることもあるようです。
金婚漬けの名前の由来
金婚漬けというのは何といってもその名前が特徴的です。
「金婚」といえば、金婚式で使われていますね。これは一般的に夫婦が50年以上一緒に過ごした場合に使われるものです。
名前の由来は、いくつかの説があるようです。
一つは、夫婦のように、時間がたてばたつほどいい味が出るという意味を込めて金婚漬けとしたという説です。
もう一つは、岩手県の近海で取れるナマコのことを「キンコ」と呼んでおり、これが金婚漬けの見た目がこのナマコと似ているから、という説があります。
比較用に、キンコの見た目は下のようなものです。水中だとあまり似ているようには見えませんが、乾燥させて食用にしたものとは似てるのかもしれません。

金婚漬けの歴史
金婚漬けはいつごろから作られ始めたのかははっきりとはわかっていないようですが、江戸時代の末期には存在したとみられています。
一般に漬物は、保存設備や冷蔵設備が整っていない時代の保存食として作られてきたという背景があります。金婚漬けもそのような需要があったことは簡単に想像できます。
そして、戦後の1960年代あたりからは商品化が進み、現在では通販でも手に入るようになりました。
まとめ
- 金婚漬けは、岩手県の花巻などで伝統的に作られている漬物。
- 断面の美しさが特徴であり、これはニンジンやゴボウなどで作られる。
- 金婚の名前の由来は、夫婦のように長く漬け込むとよい味になるからという説や、キンコと呼ばれるナマコに似ているからという説がある。
中の具材で絵柄を作ったりしても面白そうですね。