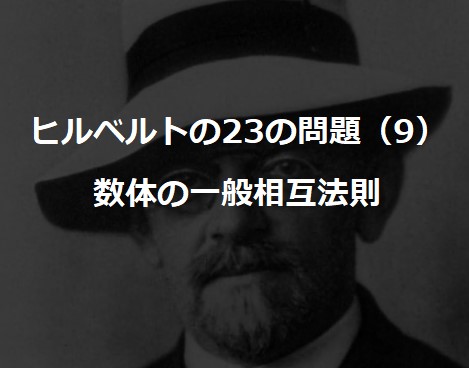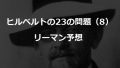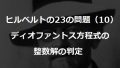みなさん、こんにちは!
今回は数学の中でもかなりディープな話題、ヒルベルトの23問題の第9番目、「数体の一般相互法則」について解説します。
数学好きも、ちょっと苦手な方も、なるべくわかりやすく説明しますので、ぜひお付き合いください!
そもそも「相互法則」って何?
相互法則(相互定理)とは、簡単に言うと、
「数の性質が国際的なルールみたいに秩序立ってつながっている」ことを示すものです。
例えば、中学校の時に習う「2の剰余がある条件の時、3の剰余がこうなる」みたいなルールの、超高度版が数学の世界にはあります。
そして、これが代数体と呼ばれる数学の世界での“数の国”のルールになっています。
代数体ってなに?
「代数体」って聞いてもピンとこないかもですね。
簡単に言うと、“普通の数の世界をちょっとだけ拡張した世界”のこと。
普通の数字は整数や分数、小数くらいですが、
代数体は、
例えば「√2」や「√3」みたいな“新しい数字”を加えた数の世界のことです。
この世界の中で、どんなルールが成り立っているのかを探るのが数学の面白いところ!
ヒルベルトの第9問題って?
ダヴィッド・ヒルベルトが1900年に発表した23の数学の未解決問題のひとつです。
第9問題は、
「任意の代数体(簡単に言えば、数の世界の拡張)で成り立つ、最も一般的な相互法則を見つけよ」
という難しい課題。
これまでに知られていた特別なケースのルールを、
「全ての数の国で通用する」超一般的なルールに拡張する、という話です。
解決までの道のり
この問題の進展は、1927年にドイツの数学者エミール・アルティンによって大きく前進しました。
彼は「アルティン相互法則」という画期的な法則を証明し、
「アーベル拡大」(可換な拡大)という特定のケースにおける相互法則の全体像を完成させました。
この功績によって、類体論という分野が確立され、代数体のアーベル拡大に関してはほぼ完全に問題が解決したと言えます。
え、アーベル拡大って何?
これもまた難しい言葉ですが、
ざっくり言うと、
代数体の拡大の中でも、「拡大の仕方が素直でわかりやすいタイプ」だと思ってください。
数学者の間では「可換(かかん)なガロア群」と呼ばれていて、
“分かりやすいパズル”みたいな感じです。
アルティンさんはこのパズルの全ての答えを出しちゃったんですね。
でも、まだまだ謎はある!
じゃあ第9問題は解決したの?
実はこれ、部分的に解決したというのが正解です。
なぜかというと、
「非アーベル拡大」という、もっと難しいタイプの数の拡大に関しては、
まだまだ未解決な部分が多くあるからです。
非アーベル拡大って?
「非アーベル」っていうのは、
簡単に言えば「パズルのルールが複雑で、順番を変えると答えが違っちゃうタイプ」なんです。
こんなパズル、なかなか解くの難しいですよね?
実はこの未解決部分を解くために、
「非アーベル類体論」という新しい数学の研究分野が生まれています。
この部分を解決する理論は「非アーベル類体論」と呼ばれ、
数学界では「ラングランズ計画」という壮大なプログラムとして研究が進められていますが、まだ完成していません。
第9の問題が残したもの
ヒルベルトの第9の問題は、「一般の代数体における相互法則を一つの定理にまとめられるか?」という、数論界の“統一理論”への挑戦でした。そして、それに真正面から挑み、アーベル拡大に関して解決してくれたのがエミール・アルティン。その功績は、「類体論」という分野を決定的に形づくることになりました。
でも、それでおしまいではありません。
非アーベル拡大への拡張、すなわち「非アーベル類体論」は、いまだに大きな未解決分野!ここからラングランズ予想やモチーフ理論、そして現代的な数論幾何学へとつながる壮大な道が開けていきます。
つまり、ヒルベルトの第9問題は、
「類体論を完成させ、さらに次の大問題(第12、ラングランズなど)を呼び込む」
という、まさに歴史を動かす“起爆剤”だったわけですね!
まとめ
- 第9問題は「数体の一般相互法則」を求める問題
- 1927年、エミール・アルティンがアーベル拡大に対して解決
- 非アーベル拡大に関しては未解決のまま
- 非アーベル類体論は現在も研究が続けられている
ヒルベルトの23問題はどれも奥が深いですが、特に第9問題は数学の中で「数の拡大の謎」に挑み続けるロマンあふれる話です。
これからも数学の世界は広がり続けるので、みなさんも一緒に楽しみましょう!