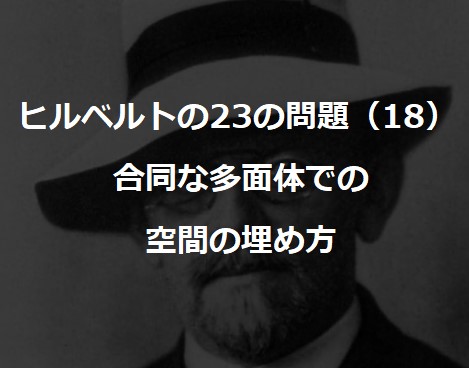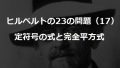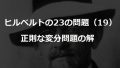こんにちは!
「ヒルベルトの23の問題をすべて解説し終えるまで帰れない」このガチンコ企画、いよいよ第18問までやってきました!
そして今回は、まさかの展開!
🟡 ケプラー予想まで出てきちゃう!
🧊 1種類の多面体だけで空間を埋められるの!?
🔢 群論・結晶構造・3Dタイル張りの世界!
という盛りだくさんな内容!
でもご安心を。この第18問、なんと…
✨全部!ちゃんと!完全に解決済み✨
今回のブログは、数学の美しさと人類の知恵がギュッと詰まった回になりますよ〜!
🧊合同な多面体で空間を埋めるってどういうこと?
まず、日常的なイメージから始めましょう。
- キッチンの床にある正方形のタイル
- サッカーボールの五角形と六角形のモザイク
- 蜂の巣の六角形
これらはすべて、「ある図形を敷き詰めて空間を埋めている」例です。
これを数学的には「タイリング(tiling)」とか「空間充填(space filling)」と呼びます。
じゃあこの「図形」が「合同な多面体」だったら……?
そう!つまりこういうこと👇
「1種類の同じ多面体だけで、3次元空間をスキマなく埋めることってできる?」
「できるとしたら、どんな図形が可能?」
「もっと高次元だと何が起きる?」
これが、ヒルベルトの第18の問題なのです!
🧠問題はなんと3つに分かれてる!
この第18問、実は3部構成になってます。それぞれ見ていきましょう!
🧮(a) n次元ユークリッド空間には「本質的に異なる空間群」は有限個か?
これは「空間群(space group)」と呼ばれる対称性の数学的なグループに関する問題。
空間群とは:対称性(回転・移動・鏡映など)をもつ図形の集合に対応する数学的構造
そしてこの問いはこう言ってます👇
「任意の次元nに対して、本質的に異なる空間群の数って有限なの?」
別の言い方では、ユークリッド空間において「対称的に空間を埋めるグループ」がどれだけあるか、という問題。
感覚的には、「どんな種類の結晶構造があるか数えられるか?」といった感じです。
この問題は、結晶学・幾何学と密接に関連し、理論的にも技術的にも応用される分野。
🔷(b) 3次元で「異面体タイル」だけの多面体は存在するか?
ここでいう「異面体タイル」とは:
「ある多面体が、全く同じ形なのに、隣接するタイルとは接する面が違うようなタイル張りをすること」
ヒルベルトはこう問いかけたわけです👇
「1種類の多面体だけを使って、タイル張りするとき、隣接のしかたが全部異なるようなものって存在するの?」
これは直感的には「えっ、そんなことできるの?」と思いますが……
イメージとしては、レゴブロックを同じ形だけ使って、でも全部違う角度で組み上げていくようなもの。
そんな不思議なタイル、多面体で本当に可能なのか?
🧊(c) 球を最も密に詰められるのはどんな方法?
ここで出てくるのが有名な:
🟡 ケプラー予想(Kepler Conjecture)!
これは17世紀の天文学者ヨハネス・ケプラーがこう予想したものです👇
「球をもっとも密に詰めるには、オレンジを箱に詰めるときのような“フェイス・センタード・キュービック格子”が最も効率が良いのでは?」
要はスーパーの果物売り場みたいな並べ方がベストって話。
この問題はフェルマーの最終定理より長い間、誰も証明できずに未解決だったことはよく知られています。
確かに直感では「これ以上うまくは詰められなさそう…」と思いますが、
「直感」と「数学的証明」は別物です。
この問い、実に400年以上も未解決のままだったのです。
🛤️解決までの道のり:地道で多様!
この第18問、実は一つ一つのパートで解決者も方法もまったく異なるのが面白いんです。
| パート | 解決者 | 解決年 | 方法 |
|---|---|---|---|
| (a) 空間群の有限性 | ビーベルバッハ | 1911〜1912 | 群論・結晶学 |
| (b) 異面体タイル | ラインハルト | 1928 | 幾何的構成 |
| (c) 球の最密充填 | ヘイルズ | 1998〜2014 | コンピュータ補助証明(Flyspeckプロジェクト) |
このように、第18問は「純粋数学 × 幾何学 × コンピュータ」の融合でもあるんですね!
🧑🔬誰がどうやって解決した?
ここからが感動のストーリー!
それぞれのサブ問題に対して、ちゃんと歴史に残る「解決者」がいます!
✅ (a) 空間群の有限性 → リュートヴィヒ・ビーバーバッハ(Ludwig Bieberbach)
この問題、結論としては・・・
✅ 有限である!
ということで、この問いは1920年代にドイツの数学者リュートヴィヒ・ビーベルバッハ(Ludwig Bieberbach)によって証明されました。
彼の名をとって「ビーベルバッハ予想」とも呼ばれ、その後の結晶学や物理でも超重要な理論に!
- 解決年:1911年〜1912年
- 内容:n次元のユークリッド空間における「本質的に異なる空間群は有限である」ことを証明
- 意義:後の結晶学や対称性理論の基礎になった!
✅ (b) 異面体タイル → カール・ラインハルト(Karl Reinhardt)
この問題、結論としては・・・
✅ 存在する!
それを示したのが、ドイツの数学者カール・ラインハルト(Karl Reinhardt)!
彼は1928年に「異面体タイル張りを許容する多面体」の存在を示しました。
- 解決年:1928年
- 内容:1種類の多面体で異面体的に空間を埋めることが可能な具体例を構成
- 意義:非周期的タイル張りなど、のちの数学や芸術(ペンローズ・タイル等)への道を開いた!
✅ (c) ケプラー予想 → トーマス・ヘイルズ(Thomas Hales)
💻 1998年〜2005年にかけて、トーマス・ヘイルズ(Thomas Hales)がコンピュータを使って証明!
なんと、
- 数千ページにおよぶ証明文書
- 数十万行のコードと検証
- 数年に及ぶピアレビュー
を経て、2014年に正式に認定されました!
これにより:
✅ ヒルベルトの第18問、完全に解決!
となったわけです!
- 解決年:1998年(初稿提出)、2014年(形式検証完了)
- 内容:コンピュータを使った膨大な検証と証明で、球の最密充填の最適解がケプラーの方法であることを証明
- 特徴:形式検証プロジェクト「Flyspeck」により証明の完全性が確認された、現代的数学の金字塔
ヘイルズの証明(1998年)は2025年現在、ヒルベルトの23の問題の中で完全解決されたものとしては最も新しい事例です。
逆に言うと、21世紀に入ってからは「新たに完全に解決されたヒルベルト問題はひとつもない」ということになります。
この事実は、ヒルベルト問題の難しさと、20世紀の数学者たちの執念を物語っていますね。
📚第18問が残したインパクト
🔬 科学への応用がスゴい!
- ビーバーバッハの理論は、結晶構造・物質科学・対称性分類に直結!
- ラインハルトの発見は、非周期性・準結晶・芸術的タイル模様の世界へ!
- ケプラー予想の解決は、コンピュータ数学・形式証明の先駆けに!
💡 数学のジャンル横断っぷりがスゴい!
この1問だけで:
- 幾何学
- 群論
- 離散数学
- 数学的証明支援ソフト
- 数学史と物理学の融合
という超広範なジャンルをカバーしています。すごすぎる!
📚第18問が残したもの
この問題の影響はめちゃくちゃ広いです!
🔬 結晶学・物理学での応用
- 原子の並び方(結晶構造)も、空間群の理論をベースに理解されている
- ケプラー予想は材料工学やナノ構造の設計にも影響
🧠 コンピュータによる証明の先駆け
- ヘイルズの「Flyspeckプロジェクト」は、コンピュータ補助証明の歴史的マイルストーン
- その後、形式検証(formal proof)という分野が発展
📝まとめ:合同な多面体の旅、完結!
というわけで、今回の第18問はヒルベルト問題の中でも、
🔓 全部がハッキリ解決されていて
🔬 現代科学にも直結していて
💡 解法もバラエティ豊か!
という「完全勝利回」でした!
✍️今回の要点まとめ(箇条書き)
- 第18問は「空間を合同な多面体でどう埋められるか?」を問う問題
- (a) 空間群の数は有限か?→ ✅ ビーバーバッハが解決(1911)
- (b) 異面体タイリングは可能か?→ ✅ ラインハルトが解決(1928)
- (c) 最も密な球の詰め方は?→ ✅ ヘイルズがコンピュータで証明(2014)
- この問題は幾何学、結晶学、形式検証の世界に深く影響
- 第18問はヒルベルト問題の中でも最も「美しく解決された」問題の一つ
次回はどんな問題が飛び出すか!?
「帰れま23」、いよいよラストスパートに入ってきました🔥
今回も読んでくれてありがとう!