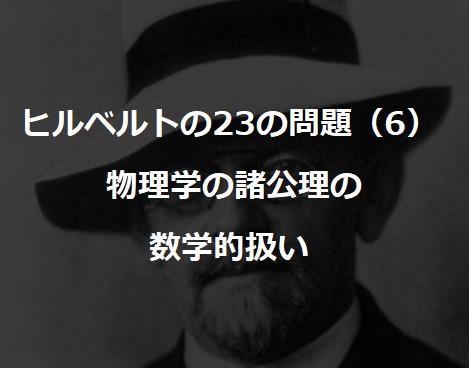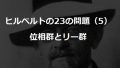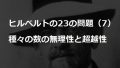こんにちは〜!
「ヒルベルトの23の問題を全部解説するまで帰れま23」シリーズ、第6回に突入しました!
「この世界の物理的なルールって、ぜんぶ数式で説明できるの?」
そんな壮大な問いに挑んでいるのが第6の問題です。
彼が1900年に掲げた23の難問の中でも、今回取り上げる第6問題はちょっぴり変化球。なんと「物理学を公理で定義しようぜ!」というのです。今回はこのちょっと難しそうなテーマを、ポップに解き明かしていきます♪
第6問題「物理学の諸公理の数学的扱い」とは?
それがこちら!
「物理学の諸公理の数学的扱い」
つまり、「物理の法則って、全部数学的にちゃんと“ルール化”できるの?」という問いです。
「ニュートンの運動法則」「エネルギー保存の法則」…私たちが学んできた“物理の常識”を、数学的に厳密に扱うにはどうしたらいいのか?という壮大なテーマなんです。
そもそも“公理”ってなに?
まず最初に、「公理」という言葉から確認しましょう。
公理(こうり)とは、「当たり前すぎて証明がいらない前提」のことです。
たとえば、
- 「2つの点があれば、それらを結ぶ直線は1本だけ存在する」
- 「1+1=2」
といったものが公理です。
数学では、公理を土台にして、いろんな理論や公式を組み立てていきます。
では、この“公理”の考え方を物理にも適用できるのでしょうか?
物理を公理で表現できるのか?
ヒルベルトが問題として掲げたのは、「物理現象を数学のように厳密な“公理系”で表現できるのか?」ということでした。
つまり、数学だけでなく物理の世界をもまきこむ大きな野望と言えます。
これには大きく分けて2つのアプローチがあります。
(a) 統計物理と確率論の公理化
私たちの身の回りの現象の中には、「確率的にしか分からない」ものもたくさんあります。
たとえば、気体の分子の動きや、熱の広がり方などは、1つ1つの粒子の動きを完璧に追いかけることはできません。
そこで登場するのが、「統計物理学」という分野です。
これは、たくさんの粒子の動きをまとめて“平均的に”扱う方法ですね。
でもここで問題が。
「そもそも“確率”って何?」という、ちょっと哲学っぽい疑問が出てきます。
ボルツマンの貢献
この課題に対して重要な役割を果たしたのが、ルートヴィッヒ・ボルツマンという科学者です。
彼は、粒子の運動と熱の関係を説明するために、統計力学という理論を築きました。
その中で「エントロピー」や「ボルツマン方程式」といった概念を導入しています。
ヒルベルト自身も、ボルツマンの業績には高い評価を与えており、「彼の方法が公理化の鍵になるかも」と考えていたようです。
(b) 原子から連続体への極限理論
次に注目したいのが、「原子論的な視点から、連続体の法則を導けるのか?」という問題です。
ちょっと難しそうに聞こえるかもしれませんが、身近な例で考えてみましょう。
たとえば、空気はなめらかに流れるように見えますよね。でも実際は、無数の小さな分子がぶつかり合ってできているのです。
このように、ミクロな世界(粒子や原子)と、マクロな世界(流体や音波などの連続的な現象)を“数学的に”つなげたい。
それがヒルベルトの狙いでした。
解決までの道のり
物理を公理で整備するという試みのこの問題は、1933年に大きな成果を迎えます。
コルモゴロフの登場!
この疑問に、1933年、ロシアの数学者アンドレイ・コルモゴロフが答えました。
彼は、確率の公理系を打ち立てたのです!
これにより、「確率とはこういうルールで動くものですよ」ということが、数学的に定義できるようになりました。
今でもこのコルモゴロフの公理は、確率論の教科書に当たり前のように載っています。
つまりこの分野では、ヒルベルトの第6問題に対する「部分的な解決」が成し遂げられたといえるのです。
量子力学の公理化という新たな壁
20世紀に入り、物理学はさらに新しい世界へと突入します。
それが、量子力学の誕生です。
これは、光や電子などのミクロな世界を説明するために登場した理論ですが、あまりにも直感に反していることで有名です。
- ある瞬間に、電子が「どこにあるか」は確率的にしか分からない
- 観測することで状態が決まる?
…などなど、不思議すぎるルールがいっぱい。
こんな量子の世界を、「ちゃんとした数式と公理で説明しよう」と立ち上がったのが、
ジョン・フォン・ノイマンです!
1932年、彼は『量子力学の数学的基礎』という本を出版し、量子力学の定式化に挑戦しました。
彼のアプローチでは、「ヒルベルト空間」という数学的構造を使って、量子の状態や観測を扱うようにしました。
でも、これですべてが片付いたわけではありません。
量子の謎は深く、今もなお「公理的にどう定式化するか」は研究が続いているのです。
結局、第6問題は解決されたの?
ここまでの流れを見ると、答えはこうなります。
部分的には解決されているけれど、完全にはまだ!
- 確率論はコルモゴロフによって数学的に整理されました。
- 統計物理や連続体への極限理論も、一定の進展がありました。
- 量子力学に関しては、フォン・ノイマンによる初期の公理化がありましたが、完全な答えは出ていません。
つまり、ヒルベルトの第6問題は「現在進行形の課題」といえるのです!
第6の問題が残したもの
ヒルベルトの第6問題は、100年以上経った今でも私たちに大切なメッセージを残しています。
それは、
「物理の世界をただの経験則で終わらせず、数学の言葉で厳密に説明しよう!」
という強い想いです。
この問題のおかげで、確率論の公理化や量子力学の数学的基礎づくりといった、現代物理学の柱となる研究が進みました。
具体的には、
- 確率論の公理化が進み、統計物理学が数学的にしっかりした基盤を得たこと
- ボルツマンの統計力学や「極限過程」の理論化が促され、ミクロからマクロへの橋渡しが深まったこと
- 量子力学の数学的基礎づくりが加速し、フォン・ノイマンの公理体系などが生まれたこと
こうした成果は、現代物理学の土台を築き、より精密で再現性の高い理論構築を可能にしました。
また、この問題が提起されたことで、物理学者と数学者が協力し合う研究も盛んになり、学問の垣根を超えた新しい発想が次々に生まれています。
そして何より、「まだ解決していない」と知ることで、未来の数学者・物理学者に新たな挑戦の火を灯し続けています。
つまり、第6問題は、
- 科学をより深く理解するための道しるべ
- 未来へのバトン
として、今もなお輝きを放っているのです!
🌟まとめ:ヒルベルト第6問題ってこういうこと!
最後に、今回の内容をサクッとおさらいします♪
✅ ヒルベルト第6問題のポイント
- 物理法則を公理的に定義しよう!という試み
- 確率論は、コルモゴロフが1933年に公理化に成功
- 統計物理と極限理論は、ボルツマンの業績を通して進展
- 量子力学の公理化は、フォン・ノイマンが取り組んだが、今も研究が続く
- 結論:完全な解決ではなく、部分的な進展にとどまっている
これから物理学を学ぶ方も、研究者を目指す方も、あるいは「なんか理系っぽい話が好き!」っていう方も、第6問題のような壮大なテーマに触れると、ワクワクしてきませんか?
次回は「超越数」を扱う問題の登場です!しばらくぶりに(?)肯定的に解決済みの問題なので、どんな話題が飛び出すかお楽しみに〜!